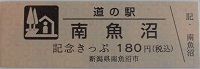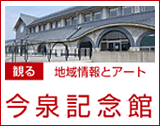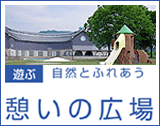【ゆきあかり通信】藤田嗣治の描く“素晴らしき乳白色の肌”
道の駅南魚沼のブログ、第二回目のテーマは藤田嗣治です。
映画「FOUJITA」が大絶賛で今話題の藤田嗣治ですが、簡単にご紹介するとピカソに才能を讃えられ、フランスで最も成功した日本人画家です。
藤田といえば裸婦像が有名ですが、1922年に『寝室の裸婦キキ』が発表されると、「素晴らしき乳白色の肌」と西洋画壇に大絶賛され一大センセーションを巻き起こしました。藤田の代表作であるこの絵をきっかけに、藤田は一躍パリ派を代表する画家になりました。『寝室の裸婦キキ』はピカソら巨匠の絵と並び、パリ市立近代美術館に展示され世界中の人々を魅了してきました。
また、1923年の作品『裸婦』に見られる、白く透き通った肌の質感は「美術史において初めて肌の描写を芸術にした」と称賛されるほどのものでした。
藤田はピカソのアトリエで見たルソーの絵画に衝撃を受け、独自の画風を追及し、試行錯誤を繰り返しました。そこで参考にしたのが、小さい頃から好きだった北斎をはじめとする浮世絵です。極限までデフォルメされた輪郭線や、なめらかな墨の描き方からもそれがうかがえます。
また、一見すると平面的に見える肌ですが、近年の化学調査でベビーパウダーの原料であるタルクを使用していることが分かりました。タルクを肌部分にのみ使用することでテカリを抑え、温かみのある独自の質感を表現したのです。現に晩年彼のアトリエから多量のタルクが発見され、また土門拳が撮影したアトリエの写真にもタルクが写っていました。
そして白い肌を際立たせる繊細な輪郭線は、浮世絵にも用いられている面相筆を使用しました。面相筆は元々細く描ける筆ですが、藤田は更に筆の中に針を仕込むことで、極細の線を均一に引いていました。実はここにもタルクが重要となってきます。というのもそのまま墨を描いたのでは、水性の墨ははじかれてしまうため、タルクを使用することで油絵の上に墨を置くことを可能にしました。こうして藤田の代名詞である「乳白色の肌」が確立されたのです。
6月15日(水)まで今泉記念館アートステーションで開催されている企画展「藤田嗣治とヴラマンク生誕記念展~パリ派と野獣派~」で藤田作品を展示していますが、中でもおすすめは『横たわる二人の裸婦』です。
残念ながらこの作品は銅版画ですが、藤田は繊細な描線を出しやすい銅版画に好んで取り組み、油絵や素描では表せない独特の表現を見ることができます。
また、この作品に出てくる黒髪の女性は、藤田を一躍有名にした『寝室の裸婦キキ』のモデルのキキ(本名アリス・プラン)です。キキはパリ派の画家たちに大人気で、パリで行われた美人投票で女王に選ばれ、「モンパルナスの女王」と呼ばれていました。
藤田は「私の体は日本で成長し、私の絵はフランスで成長した」と述べているように、藤田の裸婦像は日本人としての繊細な感覚や、ピカソたちとの交流などパリでの経験とが合わさって生まれた日本と西洋との融合作品とも言えるのではないでしょうか。
また、面相筆と墨があるアトリエが描かれた『自画像』も展示しています。この機会にぜひ藤田作品をご覧下さい。